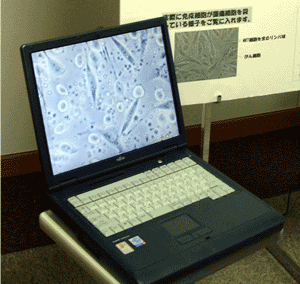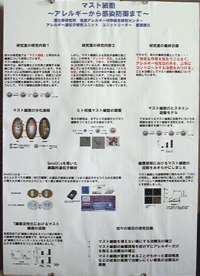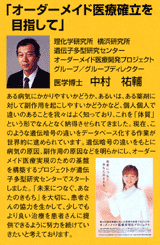これは薬品の効果が及ぼされる部位での患者の体質の違いなのではないか?少なくとも調査する意味合いはあるだろう。もしも薬品Xはa,bさんに有効で、a,bさんに特有な遺伝子的特徴が存在すればその薬品はa,bさんに特有な有効性があることとなる。薬品Yも同様である。そのように薬品に遺伝子多型ごとの有効情報を付加することが出来れば(そのような研究が行われれば)無効な薬を「その疾患にはこの薬」といって単純に副作用のリスクを孕みながら服用することなくより安全に有効な薬を選択できるのではないかということである。
2003年11月3日にFDA(米食品医薬品局 )は「遺伝子も含む副作用を調べるべき」とのガイダンスを出した。薬品の副作用には患者の遺伝子を含む様々な体質的問題が背景に存在するのではないか?と問いかけている。また、日本では「イレッサ/ゲフィチニブ / ZD 1839 / gefitinib 」に関する問題が挙げられた。イレッサは2002年7月に発売され、同年8月に国内で薬価収載された手術不能又は再発非小細胞肺癌 に用いられた薬品である。日本人においては副作用評価対象例 51 例中 50 例( 98.0 % )に副作用が認められ、主な副作用は、発疹 32 例( 62.7 % )、下痢 25 例( 49.0 % )、そう痒症 25 例( 49.0 % )、皮膚乾燥 17 例( 33.3 % )等であった。 外国の副作用集計では副作用例が73.1%(以上アストラゼネカ株式会社 提出資料より)であることから日本人には副作用が出やすいと考えるべきであろう。医師は承認された医薬品イレッサを用いて有効例となりそうな300名/1000名を探すこととなる。しかし、投与を続ければ続けるほど10名/1000名の確率で生命に関わる副作用が出るという現実を目の当たりにすることになる、というわけである。実際、現実は抗ガン剤は「やってみてなんぼ」の世界であり、今ではイレッサでは副作用に注意する様になって20〜30%が有効になる様になってきた。しかし、遺伝子で有効性を想定できる様になってきたとのことである。さらに先生はガン細胞自体の遺伝子の特性を調べ、抗ガン剤の有効性を定数化しようとしているそうである。この様に21世紀型オーダーメイド医療をを実現したいと先生は述べられた。
さて、遺伝子の情報に関しても光と影がありそうである。
米上院は2003年10月14日、健康保険への加入や就職・解雇の際、保険会社や雇用主が個人の遺伝情報を判断材料として使うことを禁止する法案を95対0(棄権5)で可決した。連邦レベルの規制がない現状では遺伝子の違いで差別するケースがあり、それを恐れるあまり必要な検査を受けない人も少なくない。法案が成立すれば、病気の早期治療や遺伝子研究の進展につながると期待されている。法案は、保険会社に対し、加入希望者の遺伝情報を事前に調べることを禁じた。遺伝情報をもとに加入を拒否することはもちろん、保険料割引などで加入者を「区別」することも認められない(以上、朝日新聞より)。
この様に遺伝情報が明らかになるにつれ、その情報をもとに人(世界中に一つしかない遺伝子情報を持つ)を差別することはいけない、という判断が下されているのである。先生はスニップならぬ「スマップ」の「世界に一つだけの花」の歌詞を引用し、これが遺伝子の話と符合する、と述べられた。
約1時間という限られた時間で、様々な情報をわかりやすく、的確に説明された中村先生。先生の様な方が日本の医学を牽引していかれればいいな、と感じる有意義な講演だった。日本におけるオーダーメイド医療の確立のために様々な対象疾患の方々が少量の血液を提供し、未来の、新しい医療が花開く日が来ることを待ち遠しく感じた。興味のある方はオーダーメイド医療実現化プロジェクトまでアクセスして頂きたい。 以上(2004年7月2日作成)
※このレポートは院長の受講した講演のレポートであり、大磯治療院と理化学研究所との関係はございませんので申し添えます。禁複製、禁配布お願い致します。 |